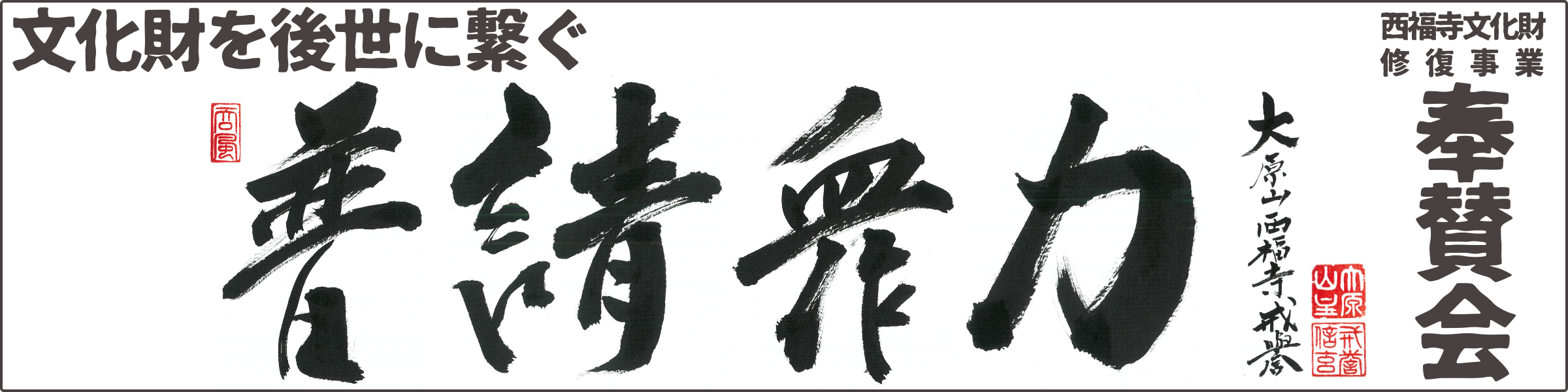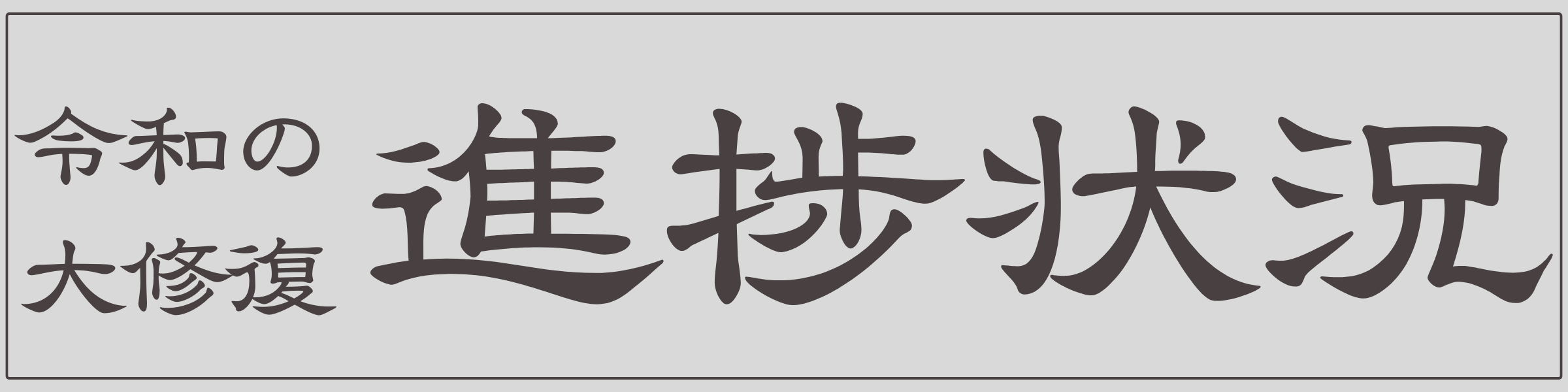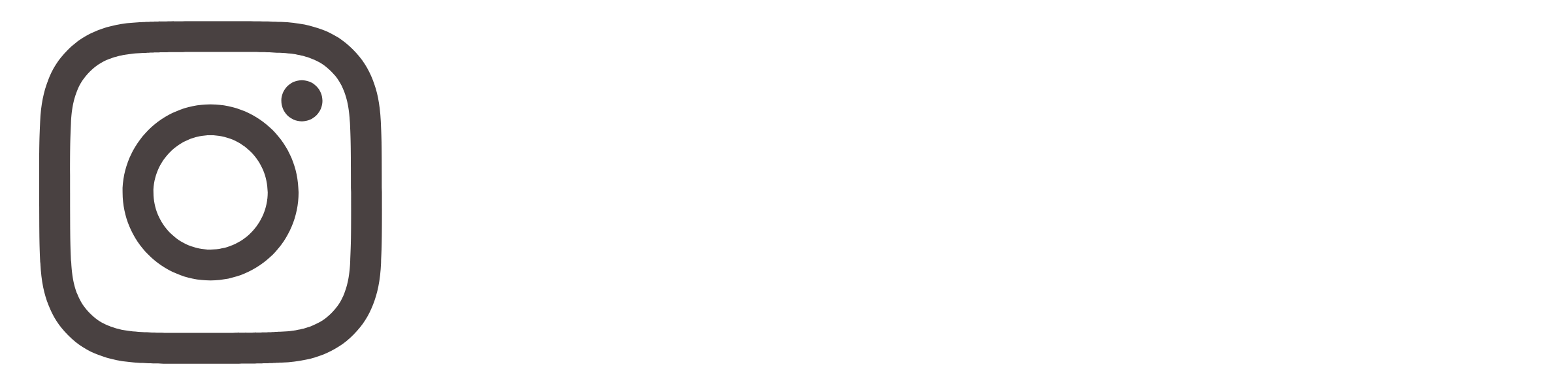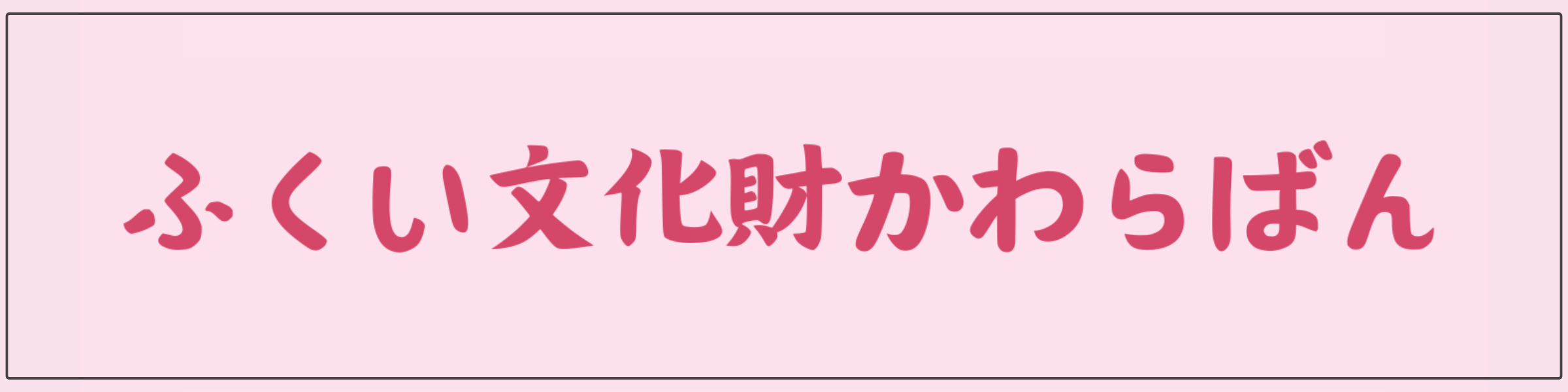沿 革

開山良如上人が諸国行脚の道すがら近江路を経て敦賀に遊化された折り、遥か西方の山中に光明輝く阿弥陀三尊の尊い御姿を感見せられて、その光明に導かれこの地に歩みを進め辻堂の辺りまで来られると、突如、一匹の白狐が現われ、上人を山の麓まで案内して忽然と姿を消した。すると見る間に阿弥陀三尊も大岩と化したと伝えられます。
そこで開山良如上人は ”仏法有縁の地である” としてこの奇瑞の山腹に一宇建立を発願せられました。後この岩を三尊石と称え、現に当寺裏山の中腹にあり、白狐も守護神としえ御影堂裏に祀ってあります。時に正平23年(北朝応安元年、1368年)3月であります。直ちに朝廷の許しを受け、時の征夷大将軍足利義満公の助力を得て堂塔を完備し、”大原山西福寺”の寺号を勅賜され建立の大願を果たされました。
爾来北陸の名刹として法灯相栄え、縁故寺院48寺、信徒1000名をこえる偉容を今日に伝えています。特に書院庭園は国の名勝庭園として有名であります。平成20年6月には全山が国の重要文化財に指定されました。